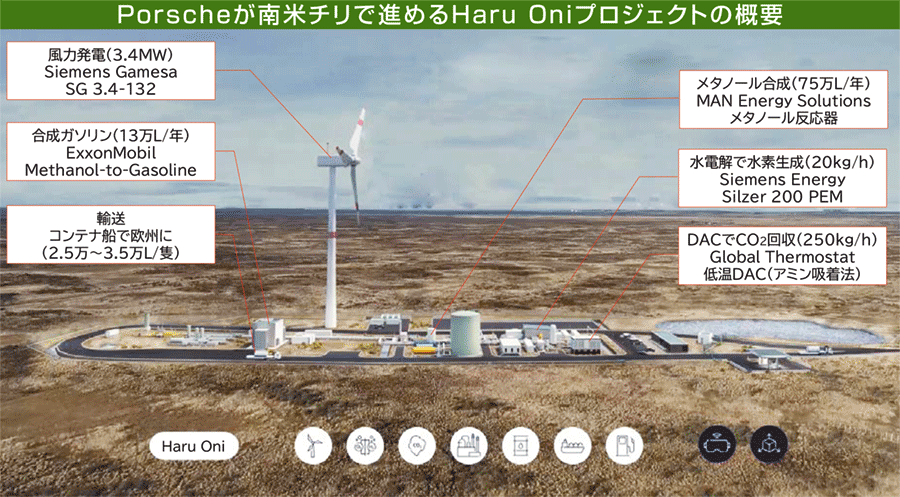調査報告書:世界
モビリティの炭素中立を実現するラストピース
- 主要国の自動車環境規制と規制上のeFuelの扱いを簡潔に解説!
- さまざまなeFuelの生産ルートと自動車分野での可能性を整理!
- 主要団体が発表したeFuelのコスト分析と普及シナリオを列挙!
- 世界のeFuelプロジェクトの生産方法と生産規模を一覧で概観!
- 自動車メーカーの取り組みと立場の違いを関係者の声とともに!
- 普及のカギを握る水分解とCO2回収の開発動向と課題を分析!
- エンジン/燃料/エネルギーに詳しい世界的識者の意見を紹介!
世界は炭素中立社会の実現を目指しています。中でもモビリティの炭素中立化では、電気自動車(BEV)が本命視されています。しかし、すべての市場、車種、用途、消費者ニーズをBEVだけで満たすことは不可能です。ハイブリッドや水素、合成燃料(eFuel)、バイオ燃料などを組み合わせたマルチパスアプローチが求められます。
合成燃料(eFuel)にはエネルギー効率が低い(BEVの6分の1以下)との批判がありますが、主要先進国のほとんどはエネルギーを輸入に頼っています。再生可能エネルギーは出力変動が大きく、先進国での自給率100%達成は2050年でも不可能と言われます。
地球上の局地に偏在する再生可能エネルギーを有効利用するためには、貯蔵や運搬に向かない電気エネルギーを別の媒体(気体/液体)に変換するPower to Xが欠かせません。eFuelはそのための最も有力なソリューションです。
本書では、eFuelを巡る主要な論点を網羅的に整理しました。自動車メーカーのエンジン技術者や世界的識者の声を踏まえ、自動車分野におけるeFuelの可能性を探ります。
※ 画像をクリックすると大きいサイズでご覧になれます。
| ▼1章へ | ▲PAGE TOP |
 序章 |
|
eFuelとライフサイクルアセスメント(LCA)、主な論点
|
|
| ▲序章へ / ▼2章へ | ▲PAGE TOP |
 第1章 |
|
各国規制とeFuel
|
|
EUの小型自動車CO2規制とeFuel |
EU Fit for 55でのeFuelの扱い |
EUの大型自動車CO2規制とeFuel |
EUの再生可能エネルギー指令(RED III) |
ドイツ政府のエンジン存続に関する見解とeFuel関連助成 |
米国のインフレ抑制法(IRA)とクリーン燃料 |
中国の炭素中立方針とeFuel |
日本のeFuel導入促進策 |
世界主要国のEV比率目標 |
| ▲1章へ / ▼3章へ | ▲PAGE TOP |
 第2章 |
|
eFuelと各種のカーボンニュートラル燃料
|
|
Fischer-Tropsch+共電解(JPEC) |
先進バイオ燃料 |
水素化植物油(HVO) |
| ▲2章へ / ▼4章へ | ▲PAGE TOP |
 第3章 |
|
eFuelのコストと普及の各種シナリオ
|
|
各種のコスト分析と普及シナリオ |
eFuelコスト分析~サウジアラビア~ |
eFuelコスト分析~ドイツ~ |
eFuelコスト分析~推進派~ |
eFuelコスト分析~否定派~ |
ドイツFVVのGHG最小化シナリオ |
乗用車での現実的なeFuelルート |
| ▲3章へ / ▼5章へ | ▲PAGE TOP |

第4章 |
|
eFuel開発の最前線 |
|
世界のeFuel生産プロジェクト |
世界の主なeFuel生産プロジェクト一覧 |
主なeFuelプロジェクト~世界(欧州以外)~ |
eFuel会議における議論状況 |
注目のeFuel事業者(HIF Global) |
注目のeFuel事業者(Axens) |
| ▲4章へ / ▼6章へ | ▲PAGE TOP |
 第5章 |
|
自動車メーカーとeFuel
|
|
自動車メーカー各社の取り組みと賛否 |
VWのパワートレイン戦略と代替燃料 |
VW首脳が語るパワートレイン戦略 |
VWエンジン開発者のeFuelに関する見解 |
PorscheのHaru Oniプロジェクト |
日系自動車メーカーとeFuel |
モータースポーツとカーボンニュートラル燃料 |
二輪車メーカーとeFuel |
| ▲5章へ / ▼7章へ | ▲PAGE TOP |

第6章 |
|
eFuelのコア技術 |
|
炭素回収(DAC) |
| ▲6章へ | ▲PAGE TOP |
 第7章 |
|
eFuelを巡る識者の見解 |
|
eFuel Allianceの考え方(eFuel Alliance) |
EUと世界のeFuel見通し(エンジン研究者) |
eFuelの技術的課題と社会的課題(燃料研究者) |
水素とeFuelの普及(グリーンテックコンサル) |
世界のエネルギー情勢とeFuel(元IEA理事長) |
日本のWell to Wheel(エネルギーコンサル) |